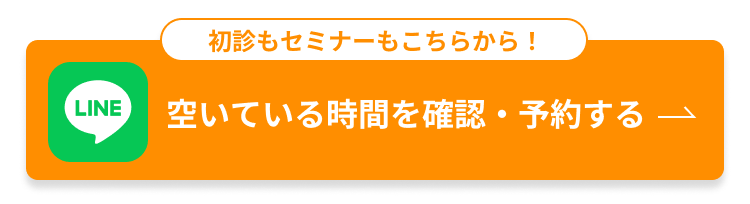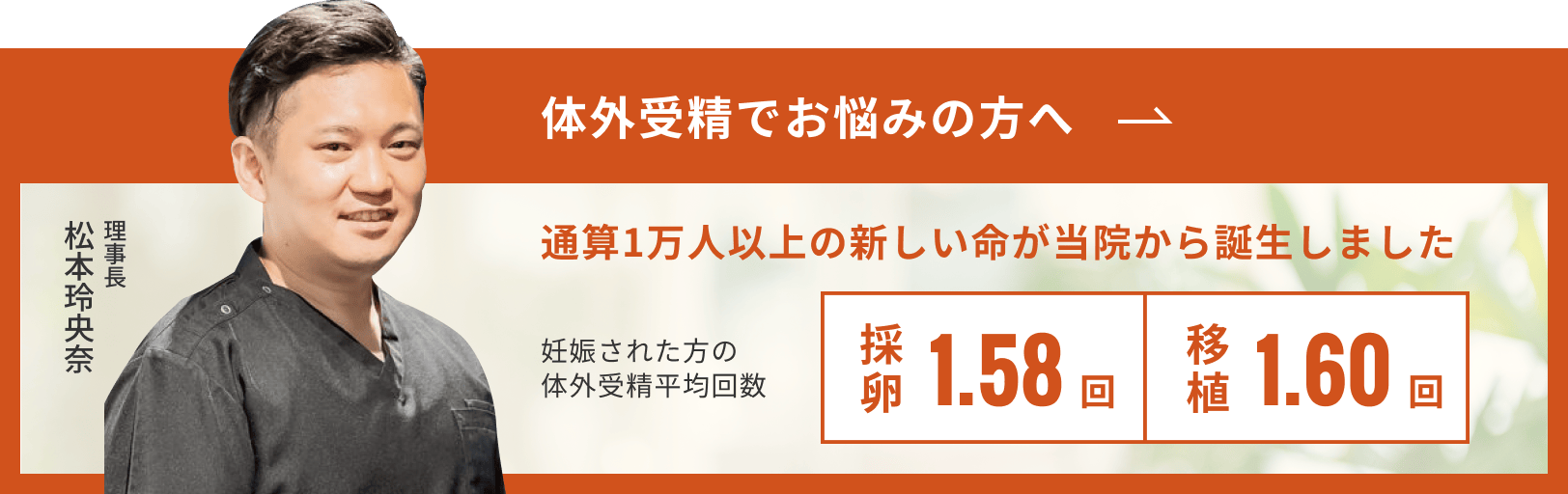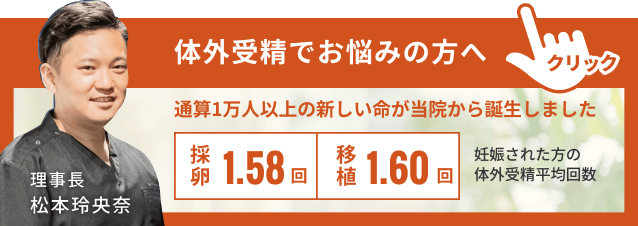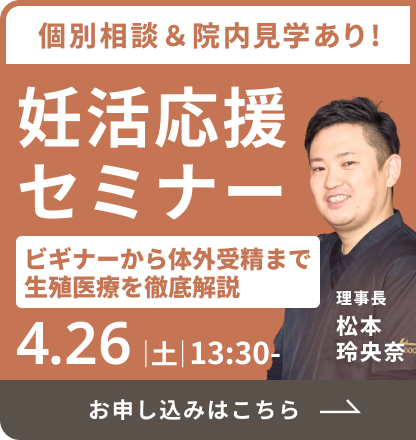2022年4月から保険適応となった体外受精は、現状で最も妊娠率の高い治療法です。内服や注射で卵胞を育てて採卵し、正常受精した受精卵を培養し、育った胚を移植して一連の流れが完結します。ところが、良い胚が育つにも関わらず、この最後の「移植」を何回も繰り返しても中々妊娠に至らない方がいらっしゃいます。その中には着床障害(着床不全)が原因である場合もあります。今回はその着床障害(着床不全)について、原因や検査、治療方法について解説します。
池袋駅 東口から 徒歩3分
働きながら、通いやすい。
最善の手段が選べる妊活を。
松本IVFレディースクリニックは、
最新のテクノロジーを駆使し、
短期での妊娠成立を目指す、
すべての人に最適な
妊活を提供します。
着床障害(着床不全)とは
着床障害(着床不全)とは、胚移植回数や移植個数に明確な定義はありませんが、少なくても良好胚を2,3回移植しても妊娠が成立しない場合を言います。
日本において体外受精・胚移植の移植当たりの妊娠率はおよそ30-40%とされており、タイミング法・人工授精の妊娠率5-10%と比べて明らかに高くなっています。その理由は様々ですが、一つには体の外で育てた良好な胚を選別して移植できることにあります。受精しなかったり、うまく育たない胚を除外できるため妊娠率は高いのですが、それでも中々着床に至らない場合があるため100%にはなりません。
着床障害(着床不全)の原因には胚側の問題と子宮側の問題、両方があると考えられています。難しいことに、着床はお腹の中で起きていることであり、その瞬間をリアルタイムで追うことはできないため、未解明な部分が多い分野でもあります。現時点では確立された着床不全に対する検査法や治療法は存在せず、少しでも着床障害を改善すべく多くの検討がなされています。
着床障害が起きる原因
①子宮の形態異常
子宮筋腫、子宮腺筋症やポリープなどがあることで子宮の形が変形する
②帝王切開瘢痕症候群
帝王切開の既往がある方で、その切開創に貯留した液が着床を妨げる
③アッシャーマン症候群
子宮内膜搔爬術(流産や中絶の際に行う手術)、帝王切開などの手術や子宮内膜の炎症により、子宮内膜に癒着が起きる
④慢性子宮内膜炎
子宮内膜に持続的な炎症がある
⑤着床の窓のズレ
受精卵を受け入れる時期(着床の窓)がずれている
⑥免疫の異常
受精卵を異物として捉えて免疫反応が働いてしまう
⑦胚側の問題
受精卵がうまく孵化できない、そもそも染色体に問題がある
着床障害の検査・治療方法
着床障害の検査
①超音波検査、MRI検査
超音波やMRIで画像的な評価をすることで、子宮筋腫や子宮腺筋症、子宮内膜ポリープ、帝王切開瘢痕症候群など、子宮の形に問題がないかを調べることができます。また、子宮筋腫がある場合などは子宮の異常な蠕動(動き)がないかを調べる場合があります。
②子宮鏡検査
子宮鏡という細いカメラを用いて実際に子宮の中を観察します。子宮内膜ポリープや中隔子宮(子宮内部に本来ないはずの薄い膜状の壁が存在すること)、アッシャーマン症候群(子宮内膜の癒着)、慢性子宮内膜炎の有無を調べます。
③ERA検査、ER Peak検査
着床の窓のズレがないかを調べる検査です。子宮内膜はいつでも受精卵を受け入れるわけではなく、その時期(着床の窓)は限られていると言われています。着床の窓が開いていない時期に移植をしても着床はできません。その窓の開いている時期には個人差があると考えられており、移植に適した時期を調べます。通常の移植周期と同じように薬で周期を調整し、本来移植するであろう日に子宮内膜の組織を採取し、その遺伝子を調べて適切な時期かを判断します。
④EMMA/ALICE検査、子宮内フローラ検査
ヒトの体には様々な部位に色々な菌が住み着いており、良い影響を与えたり、病気の原因になったりします。子宮内にも様々な菌がいることが分かっており、善玉菌が少なかったり、あるいは炎症の原因となる菌がいると着床率が低下することがわかってきました。これらの検査はその子宮内の細菌叢を調べることができます。
⑤CD138検査
慢性子宮内膜炎とは、持続的に子宮内膜に炎症が起きる疾患で、着床不全の方の30-60%に認めると言われています。ただし基本的に無症状であり、一般的なスクリーニング検査で診断することができません。CD138検査は子宮内膜組織を採取し、免疫染色して慢性子宮内膜炎に特徴的な細胞がいないかを調べる検査です。
⑥免疫の検査
ヒトの体には異物を敵とみなして排除する免疫機能が備わっています。受精卵は半分は父親由来であり母体とは遺伝子が異なるため、理論上は免疫により排除されることになりますが、免疫寛容(免疫の攻撃から守られること)が起きることで着床し発育することができます。その免疫機能(Th1/Th2比、NK細胞、ビタミンDなど)に異常がないかを調べる検査です。
⑦PGT-A
受け入れ側(子宮内膜)に問題がなくても、そもそも受精卵の染色体に異常があると着床できないか、着床できても発育が停止してしまいます。染色体は人の体を作る設計図のようなもので、そこにエラーがあると組織や臓器を正しく作ることができないためです。PGT-Aは胚の胎盤になる細胞を一部採取し、染色体の数に異常がないかを調べ、着床しない、あるいは流産の可能性が高い胚を予め知ることができます。
着床障害の治療
①子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮腺筋症などの子宮の形態異常
上記のように子宮の形が変形することで着床障害の原因となっていると考えられる場合は、手術やホルモン剤での治療が選択されます。ただし、いずれの治療でも3-6か月程度の避妊期間が必要なことがあり、女性側の年齢によってはその期間の影響が無視できない可能性があります。そのため、貯胚といって、手術やホルモン剤などの治療前に複数個の胚を凍結しておくことがあります。
また、特に子宮筋腫や子宮腺筋症の手術を行う場合は、出産方法が帝王切開になる可能性が高いこと、妊娠中に子宮破裂のリスクが高まることなどがあるため、適応は慎重に検討する必要があります。
②帝王切開瘢痕部症候群
1人目を帝王切開で出産した場合、まれにその手術で切開した傷に貯留する液体が着床に影響を与えている場合があります。この場合は、子宮鏡や腹腔鏡などを用いた手術で、その部位を部分切除して縫合することがあります。
③アッシャーマン症候群
子宮鏡を使用して癒着を剥離する手術を行います。また、再度の癒着を防ぐため、手術後しばらく子宮内に癒着防止の器具を入れ、ホルモン剤の投与を行います。
④慢性子宮内膜炎
慢性子宮内膜炎が疑われる場合は、子宮内の菌の組成を調べ、その菌に応じた抗生剤を投与して治療します。また、善玉菌とされる乳酸菌が少ない場合は、それを増やすサプリを使用することで子宮内環境を整えます。
⑤免疫異常
免疫異常が疑われる場合は免疫を抑える薬を内服します。また、ビタミンDは異常に上昇した免疫機能を適切に抑制する効果があると言われており、サプリメントを使用してビタミンD濃度を上げる必要があります。
⑥胚側の問題
着床時期をコントロールする場合は、卵巣刺激を行う採卵周期での新鮮胚移植ではなく、凍結胚移植にすることで適切な時期・ホルモン状態に調整することができます。
また、初期胚(3日目胚)移植の場合は妊娠していない原因が途中で胚の発育が停止しているのか、着床側に問題があるのかわからないため、胚盤胞まで育てて移植するのも大切です。さらに、移植の際にヒアルロン酸が多く含まれる培養液を使用したり、アシステッド・ハッチング(胚を覆う透明帯にレーザーなどで切れ目を入れることで、孵化を補助すること)などのオプションを追加する方法もあります。
また、ERA検査やER Peak検査で窓のズレがあるとわかった場合は、その結果に基づいた適切な時期に移植日をずらすことも必要です。
このように、着床不全には様々な原因があると考えられており、検査や治療も多岐にわたります。上記で説明している検査・治療の中には保険適応外のもの、先進医療に含まれるものもあります。保険診療下において、保険と自費を両立させることは混合診療となり禁止されています。一部でも自費診療を行う場合は、採卵や移植まですべて自費で行う必要があります。
一方で先進医療とは、特別に保険と同時に行ってよい自費診療であり、採卵や移植は保険で行い、認められた検査や治療の部分のみ自費で追加することができます。ただし、実施するには適応を満たしていないと行えないものもあります。
施設により行っている検査や治療、導入している先進医療は異なります。通院している病院にどのような検査を受けられるか相談してみましょう。
不妊に関するお悩みは松本レディースIVFクリニックへ
当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなかできない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。
妊娠しにくい方を対象に、不妊原因の探索、妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。
1999年に開業し、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられています。
当院の特徴につきましてはこちらをご参照ください。
https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/
まとめ
今回は着床障害(着床不全)について説明しました。治療として確立しつつある体外受精の中でも、着床については解明されていないことが多くある分野です。それでもこの10年程度の間に様々な検査や治療が考案され、着床の確率を上げる方法についても一定のエビデンスが蓄積されてきました。移植がなかなか上手くいかず悩んでいる方は、通院先の病院にどのような検査・治療を行っているか相談してみましょう。